この記事では、そんなあなたのために、素材ごとの特徴や違いを分かりやすく徹底比較します!本格的な味と香りを楽しむなら「せいろ」、手軽さと汎用性なら「ステンレス」、時短調理なら「シリコン」がおすすめです。選び方のポイントから人気商品、お手入れ方法や簡単レシピまでご紹介するので、読めばあなたにぴったりの一台がきっと見つかりますよ!
最初に結論 あなたに合う蒸し器はこれ
蒸し器が欲しいなと思っても、せいろやステンレス、シリコンなど素材も形もいろいろあって、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね!
でも大丈夫、難しく考える必要はないんです。最初に結論からお伝えすると、あなたのライフスタイルや「どんな風に蒸し料理を楽しみたいか」に合わせて選ぶのが一番の近道なんですよ。
ここでは、代表的な3つの素材「せいろ」「ステンレス」「シリコン」のそれぞれの特徴から、あなたにピッタリな蒸し器を提案しますね!
本格的な味と香りを楽しむなら「せいろ」
おうちで本格的な点心や、ふっくらと香り高い蒸し料理を味わいたいあなたには、昔ながらの「せいろ」がぴったりです。杉や檜(ひのき)といった天然木で作られたせいろは、蒸している間に木の香りが食材にほのかに移り、料理の風味を格段にアップさせてくれます。 さらに、木が余分な水分を吸ってくれるので、食材が水っぽくならず、旨味が凝縮された仕上がりになるのが最大の魅力です。 見た目もおしゃれで温かみがあるので、調理してそのまま食卓に出せるのも嬉しいポイントですね。 お手入れに少しだけ手間はかかりますが、それを上回る美味しさと楽しさがありますよ。
汎用性と手入れのしやすさなら「ステンレス製蒸し器」
「蒸し料理は楽しみたいけど、後片付けは楽な方がいいな」「毎日のお料理で気軽にどんどん使いたい!」そんなあなたには、丈夫で衛生的な「ステンレス製蒸し器」がおすすめです。ステンレスは錆びにくく、汚れや匂いがつきにくいのでお手入れがとっても簡単なのが特徴です。 油を使ったお肉料理を蒸した後でも、さっと洗剤で洗える手軽さが嬉しいですね。 お手持ちの鍋に乗せて使うプレートタイプや、鍋とセットになった専用タイプなど種類も豊富。 IH対応のものも多いので、どんなご家庭のキッチンにも合わせやすい、まさに万能選手です。
時短と手軽さを求めるなら「シリコンスチーマー」
忙しい毎日を送るあなたや、一人暮らしでサッと一品作りたい時には「シリコンスチーマー」が最高の相棒になります。カットした野菜などの食材を入れて、電子レンジでチンするだけで、あっという間に温野菜などのヘルシーな一品が完成します。 軽くて扱いやすく、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できる製品が多いのも魅力の一つ。 調理してそのまま食卓に出したり、冷蔵庫で保存したりもできるので、洗い物を減らしたいあなたにもぴったりですよ。
【一覧比較表】せいろ・ステンレス・シリコン蒸し器の違い
蒸し器っていろいろな種類があって、どれを選んだらいいか迷っちゃいますよね!素材によって、得意な料理やお手入れの方法も変わってくるんです。ここでは、代表的な3つの素材「せいろ」「ステンレス」「シリコン」の違いを、分かりやすく表にまとめてみました。これを見れば、あなたのライフスタイルにぴったりの蒸し器がきっと見つかりますよ♪
| 比較項目 | 木製せいろ | ステンレス製蒸し器 | シリコンスチーマー |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 天然の木が余分な水分を吸い、食材が水っぽくならない。木の良い香りが料理に移り、風味豊かに仕上がる。 | 丈夫で錆びにくく、耐久性が高い。熱伝導が良く、一度温まると冷めにくい保温性も魅力。 | 電子レンジで手軽に調理可能。 折りたためるものも多く、コンパクトに収納できる。 |
| 仕上がり | ふっくら、ジューシーで風味豊か。 冷めても固くなりにくい。 | 食材本来の味や香りを活かした、シンプルな仕上がり。 | しっとりとした仕上がり。時短調理でもパサつきにくい。 |
| メリット | ・本格的な味と香りを楽しめる ・食卓にそのまま出せるデザイン性 ・適度な調湿効果 |
・丈夫で長く使える ・お手入れが簡単で衛生的 ・IH対応のものも多い |
・電子レンジで時短・簡単調理 ・洗い物が少なく済む ・手頃な価格 |
| デメリット | ・カビが生えやすく、手入れに気を使う ・しっかり乾燥させる必要がある ・電子レンジ、食洗機は使用不可 |
・水滴が食材に落ちやすく、水っぽくなることがある ・無機質な見た目 |
・直火やオーブンでは使えないものが多い ・食材によっては匂いや色が移ることがある ・本格的な仕上がりには向かない |
| お手入れ | 使用後は洗剤を使わず、お湯とたわしで洗い、風通しの良い場所でしっかり陰干しする。 | 中性洗剤で丸洗い可能。 食洗機対応のものも多い。 | 中性洗剤で洗え、食洗機対応のものも多い。 |
| 得意な料理 | シュウマイ、肉まん、おこわ、蒸しパンなど、風味を重視する料理。 | 茶碗蒸し、プリン、日常の温野菜など、幅広い料理に。 | 温野菜や下ごしらえなど、毎日の手軽な一品に。 |
| こんな人におすすめ | 料理の味や香りにこだわり、調理過程も楽しみたい方。 | ひとつの調理器具を長く大切に使いたい、お手入れの手間を減らしたい方。 | 忙しい毎日でも手軽に蒸し料理を取り入れたい、一人暮らしの方。 |
素材から選ぶ 人気蒸し器の特徴とおすすめ商品
蒸し器には色々な素材があって、それぞれに得意なことがあるんですよ!見た目やお手入れのしやすさも違います。ここでは、代表的な「木製せいろ」「ステンレス製」「シリコンス-チーマー」の3つの素材に注目して、それぞれの魅力と選び方、そして人気の商品をご紹介しますね!あなたにぴったりの蒸し器を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
木製せいろの魅力と選び方
せいろの一番の魅力は、なんといっても蒸したときの木の香りですよね! 食材にふんわりと良い香りが移って、いつもの料理がワンランクアップした本格的な味わいになります。それに、木が余分な水分を吸ってくれるので、食材が水っぽくならず、ふっくらと仕上がるんですよ。 見た目も素敵なので、調理してそのまま食卓に出せるのも嬉しいポイントです。
杉と檜(ひのき)の違い
木製せいろには、主に「杉」「檜(ひのき)」「竹」などの素材が使われます。それぞれに特徴があるので、比べてみましょう!
| 素材 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 杉 | 木の香りが豊かで、食材に風味をつけたい料理におすすめです。軽量で扱いやすいのもポイント。 | 比較的安価 |
| 檜(ひのき) | 上品な香りで耐久性が高く、長く使えるのが魅力です。 美しい木目も楽しめます。 | 高価 |
| 竹 | 香りが控えめなので、食材本来の味や香りを楽しみたいときにぴったり。 耐久性があり、価格も手頃なので初心者の方にもおすすめです。 | 安価 |
初めてせいろを使うなら、価格と耐久性のバランスが良い竹製か、木の香りを楽しめる杉製から試してみるのがおすすめですよ。
おすすめの木製せいろ
日本国内でも人気の高い、おすすめの木製せいろをいくつかご紹介しますね。
- かごや 杉 中華せいろ: 手頃な価格で人気のせいろです。杉の豊かな香りを楽しみたい方にぴったりで、サイズ展開も豊富なので、一人暮らしの方から家族で使いたい方まで幅広く選べます。
- 照宝 桧 中華せいろ: プロの料理人も愛用する、横浜中華街の老舗ブランドです。 耐久性の高い国産の檜を使用しており、作りがしっかりしているため長く愛用できます。
ステンレス製蒸し器の魅力と選び方
ステンレス製の蒸し器は、なんといっても丈夫でお手入れが簡単なのが魅力です。 サビにくく、匂い移りも少ないので、肉料理から魚料理、お菓子作りまで、いろいろな料理に気兼ねなく使えます。 IHクッキングヒーターに対応している製品が多いのも嬉しいポイントですね。
鍋タイプとプレートタイプの違い
ステンレス製蒸し器には、大きく分けて「鍋タイプ」と「プレートタイプ」があります。あなたの使い方に合うのはどちらかチェックしてみてくださいね。
| タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 鍋タイプ | 専用の鍋と蒸し用の段がセットになっています。深さがあるので、茶碗蒸しやおこわなど高さのある料理も得意です。 | 本格的な蒸し料理をたくさん作りたい方 |
| プレートタイプ | 手持ちの鍋やフライパンに乗せて使います。 コンパクトに収納できるものが多く、手軽に蒸し料理を始められます。 | 収納スペースをあまり取りたくない方、まずは試してみたい方 |
おすすめのステンレス製蒸し器
デザイン性や機能性で人気のステンレス製蒸し器はこちらです。
- 柳宗理 ステンレス鍋シリーズ(深型): シンプルで美しいデザインが人気の柳宗理の鍋は、別売りのストレーナー(ざる)を組み合わせることで蒸し器としても使えます。デザイン性を重視する方におすすめです。
- ヨシカワ 満菜 二段蒸し器: 新潟県燕三条の金属加工技術で作られた、信頼性の高い製品です。 ガラス蓋で中の様子が見えるので、調理しやすいのが特徴です。
- パール金属 フリーサイズ蒸し器: 手持ちの鍋のサイズに合わせて大きさを変えられるプレートタイプの蒸し器です。 一つあると様々な鍋で使えて便利ですよ。
シリコンスチーマーの魅力と選び方
シリコンスチーマーの最大の魅力は、電子レンジで手軽に時短調理ができること! 火を使わないので、忙しい時やもう一品作りたい時にとっても便利です。軽くて扱いやすく、食洗機で洗えるものが多いのも嬉しいポイント。 折りたたんでコンパクトに収納できるタイプもありますよ。
サイズと形状の選び方
シリコンスチーマーを選ぶときは、作りたい量や料理に合わせてサイズや形を選びましょう。
- サイズ: 一人暮らしの方や、副菜を作るのがメインなら500ml〜700ml程度の小さめサイズが便利です。 家族で使う主菜を作りたい場合は、1000ml以上の大きめサイズがおすすめです。
- 形状: 定番の四角い「角型」や丸い「ラウンド型」のほか、パスタを茹でるのに便利な細長いものや、どんぶりのような形をした「キャセロール型」などがあります。 食材の形や作りたい料理に合わせて選ぶと、さらに調理がしやすくなりますよ。
おすすめのシリコンスチーマー
使いやすさやデザインで人気のシリコンスチーマーをご紹介します。
- ルクエ (Lekue) スチームケース: シリコンスチーマーの代名詞ともいえる人気ブランドです。 豊富なカラーバリエーションと、食材から出た余分な油や水分を落とせるトレイ付きのタイプがあるのが特徴です。
- ヴィヴ (ViV) シリコンスチーマー: おしゃれなデザインとカラーで、調理してそのまま食卓に出しても素敵です。 鍋のような深さがあるキャセロール型は、煮込み料理やスープ作りにも活躍します。
- 和平フレイズ マジカリーノ: 使わないときは折りたたんで薄くできるので、収納場所に困りません。 手頃な価格で、シリコンスチーマーを初めて使う方にもおすすめです。
【目的別】蒸し器の選び方ガイド
蒸し器を選ぶとき、素材の違いもとっても大事ですけど、自分の暮らしに合ったものを選ぶのも同じくらい大切ですよね!ここでは、使うシーンや目的に合わせて、どんな蒸し器があなたにピッタリかを見ていきましょう。
一人暮らしに最適なコンパクト蒸し器
一人暮らしだと、キッチンも収納もスペースが限られていることが多いですよね。そんなあなたには、少量から手軽に調理できて、場所を取らないコンパクトな蒸し器がおすすめです!
例えば、直径15cmくらいの小さなせいろなら、肉まんを1個温めたり、少量の野菜を蒸したりするのにちょうどいいサイズ感。また、電子レンジでチンするだけで温野菜や蒸し料理が作れるシリコンスチーマーは、調理から保存までできて、洗い物も楽ちんですよ。今持っているお鍋を蒸し器に変身させられる、プレートタイプの蒸し器も賢い選択肢の一つです。
家族で使える大容量の蒸し器
家族みんなのご飯を作るなら、やっぱり一度にたくさん調理できる大容量タイプが便利!週末にシュウマイや茶碗蒸しをまとめて作ったり、品数が多い日のお料理にも大活躍してくれますよ。
おすすめは、2段や3段になっているステンレス製の大型蒸し鍋。下段でスープを作りながら、上段で蒸し料理、なんて使い方もできちゃいます。本格的なせいろなら、直径24cm以上のものを選ぶと、家族分のおかずやおこわを一度に調理できて便利です。人数に合わせたサイズの目安を下の表にまとめたので、参考にしてみてくださいね。
| 人数 | せいろのサイズ(直径) | 蒸し鍋のサイズ(直径) |
|---|---|---|
| 1~2人 | 15cm~18cm | 18cm~20cm |
| 3~4人 | 21cm~24cm | 22cm~26cm |
| 5人以上 | 27cm~ | 28cm~ |
おしゃれで食卓映えするデザイン蒸し器
せっかくなら、キッチンに置いておきたくなるような、おしゃれなデザインの蒸し器を選んでみませんか?調理してそのままテーブルに出せるデザイン性の高い蒸し器なら、いつもの食卓がパッと華やかになりますよ。
木目の美しい白木のせいろや、モダンなデザインの陶器製タジン鍋などは、見た目も素敵で、おもてなし料理にもぴったり。有名ブランドのホーロー鍋にセットできるスチーマーも人気です。お気に入りのデザインを選べば、お料理の時間がもっと楽しくなること間違いなしですね!
収納しやすい折りたたみ式やプレートタイプの蒸し器
「蒸し器って便利そうだけど、大きくてかさばるのがちょっと…」なんてお悩みはありませんか?そんな方には、使わないときはコンパクトに収納できるタイプがおすすめです。
花びらのように開閉する折りたたみ式のステンレス製蒸し器(蒸し板)は、お鍋のサイズに合わせて形を変えられ、収納時は薄くなるので場所を取りません。シリコン製で折りたためるスチーマーも、キッチンの引き出しにすっきり収まります。手持ちの鍋を有効活用できるので、新しく大きな調理器具を増やしたくない方にもピッタリですよ。
蒸し器を長持ちさせるためのお手入れ方法
お気に入りの蒸し器、せっかくなら長くきれいに使いたいですよね!素材によってお手入れのコツが少し違うので、それぞれに合った方法を知っておくのがおすすめです。ここでは、素材別に蒸し器を長持ちさせるためのお手入れ方法をご紹介しますね!
せいろの正しい使い方と保管方法
木のぬくもりが魅力のせいろは、ちょっとしたコツでカビを防いで、長く愛用できるんですよ。ポイントは「乾燥」です!
ご使用前のひと手間
せいろを使う前には、全体をサッと水で濡らしておきましょう。 こうすることで、食材の匂い移りを防いだり、せいろが焦げ付いてしまったりするのを防ぐ効果があるんです。
ご使用後のお手入れ
せいろは基本的に、洗剤を使わずに洗うのがおすすめです。 洗剤の成分が木に染み込んで、せっかくの木の香りを損ねてしまう可能性があるからです。
使い終わったら、汚れが少ない場合は湿らせた布で拭き取るだけで十分です。 油汚れなどが気になる場合は、ぬるま湯とシュロのたわしなどで優しくこすり洗いしてください。
そして、洗い終わったら、とにかくしっかりと乾燥させることが一番のポイントです。 水分が残っているとカビの原因になってしまいます。 風通しの良い場所で、直射日光を避けて陰干しで完全に乾かしてくださいね。
保管するときの注意点
せいろを保管するときは、湿気がこもらないようにすることが大切です。ビニール袋などには入れず、風通しの良い場所に保管しましょう。 長期間使わない場合は、新聞紙などに包んでおくと湿気を吸ってくれるのでおすすめですよ。
ステンレス製蒸し器の洗い方
ステンレス製の蒸し器は、なんといってもお手入れが簡単なのが嬉しいポイントですよね!普段の食器と同じように、気軽に扱えるのが魅力です。
基本的なお手入れは、食器用の中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗い、水気をしっかり拭き取って乾燥させるだけでOKです。 ただ、使っているうちに焦げ付きや水垢が気になってくることもありますよね。そんな時は、汚れの種類に合わせたお手入れを試してみてください。
| 汚れの種類 | お手入れ方法 |
|---|---|
| 通常の油汚れ | 食器用中性洗剤と柔らかいスポンジで洗浄します。 |
| 焦げ付き | 鍋に水と重曹を入れて沸騰させ、しばらく置くと焦げが浮き上がって落としやすくなります。 どうしても落ちない場合は、クリームクレンザーで優しくこする方法もあります。 |
| 白い斑点や虹色の変色 | これらは水道水に含まれるミネラル分が原因です。お鍋に水と少量のお酢やクエン酸を入れて沸騰させると、きれいになりますよ。 |
お手入れの際にスチールたわしなどで強くこすると、表面に傷がついてしまう可能性があるので注意してくださいね。
シリコンスチーマーの洗い方と注意点
電子レンジで手軽に使えるシリコンスチーマーは、お手入れも簡単です。基本的にはステンレス製と同じように、食器用洗剤とスポンジで洗えます。食洗機に対応している製品が多いのも便利なポイントですね。
ただし、シリコン素材は油汚れが残るとヌルヌルしたり、食材の匂いが移りやすいという特徴があります。 気になる場合は、以下の方法を試してみてください。
匂い移りやベタつきが気になるとき
重曹とお酢(またはクエン酸)を使ったお手入れが効果的です。 耐熱容器にシリコンスチーマーを入れ、お湯と大さじ1杯程度の重曹とお酢を加えてしばらく放置すると、匂いやベタつきがスッキリしますよ。 カレーなどの色移りが気になる場合は、キッチン用の漂白剤が使える製品もあるので、取扱説明書を確認してみてください。
油汚れは放置すると落ちにくくなるので、使った後は早めに洗うことを心がけると、いつでも気持ちよく使えますね!
知っておくと便利 蒸し器を使った簡単レシピ
蒸し器を手に入れたら、まず作ってみたい定番の簡単レシピをご紹介しますね!蒸し料理は、食材のうま味や栄養を逃さず、おいしさを最大限に引き出せるのが魅力です。いつもの食材が、きっとごちそうに変わりますよ。
基本の温野菜
蒸し料理の基本といえば、やっぱり温野菜です!野菜本来の甘みと栄養を逃さず、手軽においしくいただけます。彩りも豊かで、食卓がパッと華やかになりますね。蒸したてをシンプルに塩やポン酢でいただくのはもちろん、バーニャカウダソースなどを添えるのもおすすめです。
作り方のポイント
作り方はとっても簡単。食べやすい大きさに切ったお好みの野菜を、蒸気の上がった蒸し器に入れて蒸すだけです。火の通りにくい根菜類から先に入れるのがコツですよ。竹串がすっと通るくらいになったら出来上がりです。
野菜別 蒸し時間の目安
野菜の種類によって火の通りやすさが違うので、下の表を目安に蒸し時間を調整してみてくださいね。
| 野菜の種類 | 蒸し時間の目安 |
|---|---|
| 根菜類(じゃがいも、にんじん、かぼちゃなど) | 10分~15分 |
| 実もの野菜(ブロッコリー、とうもろこしなど) | 5分~8分 |
| 葉物野菜(キャベツ、ほうれん草など) | 2分~3分 |
ふっくらジューシーなシュウマイ
おうちで手作りするシュウマイは、蒸し器を使うと格別のおいしさになります。お店で食べるような、ふっくらジューシーな仕上がりになりますよ。休日に家族みんなで皮に包むのも楽しい時間ですね。
作り方のポイント
豚ひき肉とみじん切りにした玉ねぎ、調味料をよく混ぜて作ったタネを、シュウマイの皮で包みます。蒸し器にキャベツやレタス、またはクッキングシートを敷いてからシュウマイを並べると、皮がくっつくのを防げます。蒸気の上がった蒸し器で、中火で10分~15分ほど蒸せば完成です。
なめらか茶碗蒸し
「す」が入りやすくて意外と難しい茶碗蒸しも、蒸し器を使えばなめらかな口当たりに仕上がります。火加減の調整が、なめらかな口当たりを実現する最大のポイントです。鶏肉やえび、しいたけ、かまぼこなど、お好みの具材で楽しんでみてください。
作り方のポイント
卵とだし汁をよく混ぜ合わせ、一度こしてから具材を入れた器にそっと注ぎます。蒸気の上がった蒸し器に入れたら、最初の2~3分は中火、その後は弱火にして10~15分ほどじっくり蒸すのが「す」を防ぐコツです。蓋を少しずらして蒸気を逃がすようにするのも効果的ですよ。
まとめ
あなたにぴったりの蒸し器、見つかりましたか?蒸し器とひとことで言っても、素材によって使い勝手や仕上がりが全然違うんですよね。この記事では、それぞれの特徴を比較しながら、あなたに合う蒸し器の選び方をご紹介してきました。
結論として、木の香りと本格的な仕上がりを求めるなら「せいろ」、いつものお鍋としても使えてお手入れも簡単なものがいいなら「ステンレス製蒸し器」、そして電子レンジで時短調理をしたいなら「シリコンスチーマー」がおすすめです。ご自身のライフスタイルや作りたい料理に合わせて選ぶのが、一番のポイントなんですよ。
お気に入りの蒸し器がひとつあるだけで、料理のレパートリーがぐっと広がって、食生活がもっと豊かになります。ぜひこの記事を参考に、毎日の料理が楽しくなるような、素敵な蒸し器を見つけてくださいね!
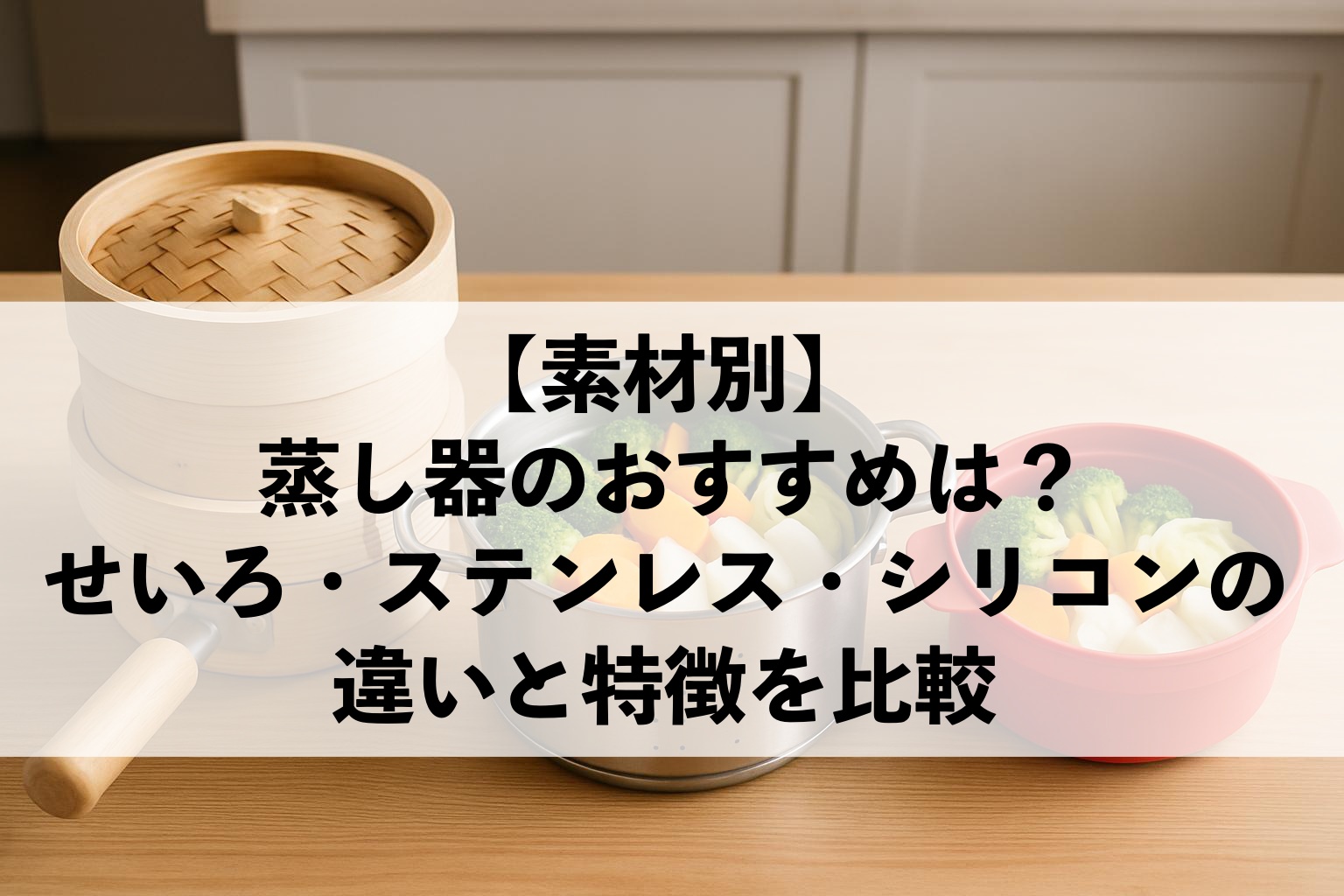
コメント